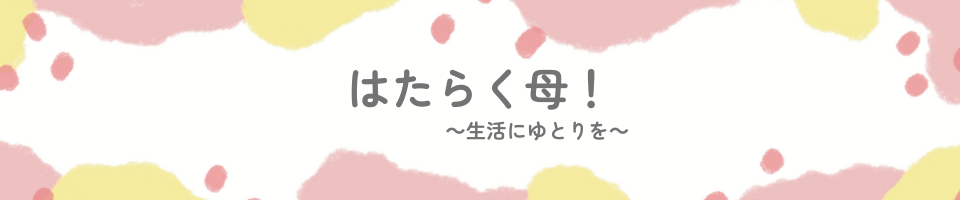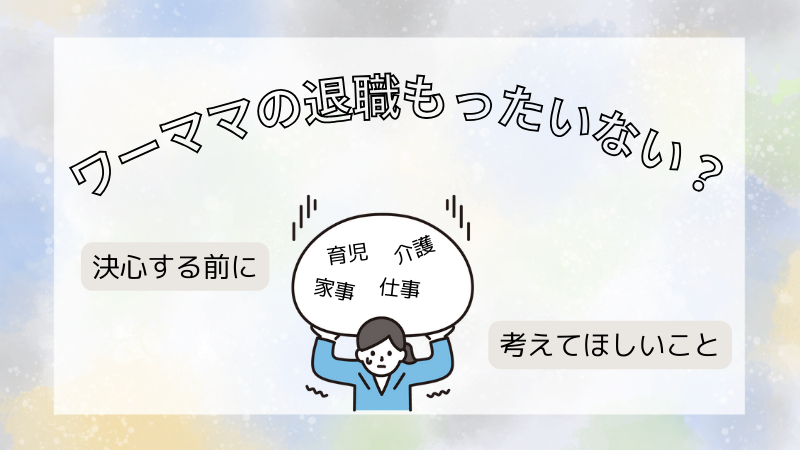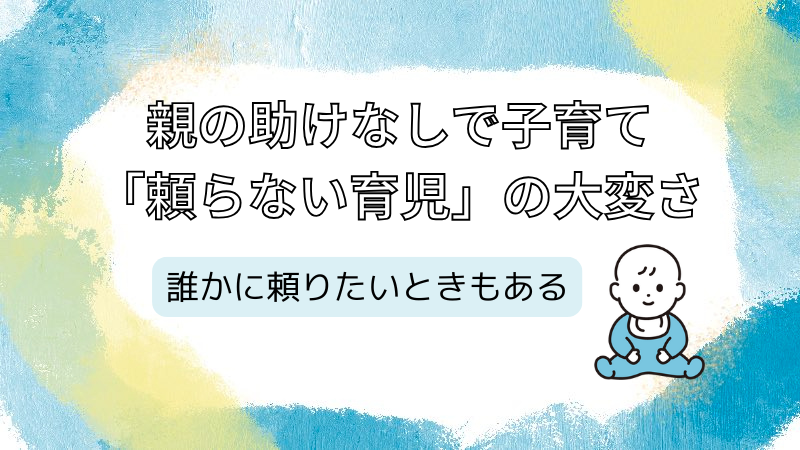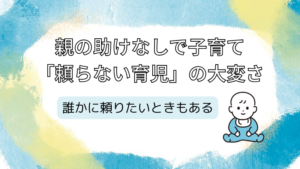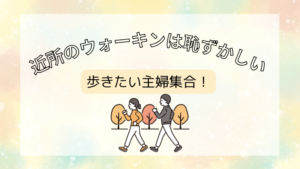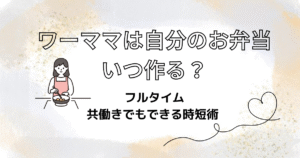ワーママとして「仕事を辞めたい」と考えるとき、そこには、さまざまな理由がありますよね。
育児と仕事の両立に悩み、退職という選択肢を思い浮かべてしまうのは、仕方のないことです。
もっと子どもとの時間がほしい。もっと時間にゆとりをもって生活したい。しかし、周りから「辞めてしまうのはもったいないよ。」と言われ、退職を悩むママも多いのではないでしょうか?
 あや先生
あや先生私は悩みに悩んで子どもが小学校に上がるタイミングで退職を選択、在宅ワークに切り替えたタイプの人間です。それはもう悩みました…。
この記事では「退職を考えるのがもったいない理由」や「考えるべき重要なポイント」について探っていきます。退職が本当に最適な選択なのかどうか、もう一度考えてみてくださいね。
この記事のポイント
・退職による弊害はやっぱり収入面
・小学校に上がったら楽になるは誤情報
・続けるための後ろ盾がない人は無理しない
働き続けるのはしんどい!退職がちらつく理由
ワーママが退職を考える理由には、体力的な負担や、家庭内でのバランスが関係しているケースが多い印象です。
とくにフルタイムで働く女性にとって、仕事と家事育児のバランスを保つことは容易ではありません。
| 体力的な負担が大きい | フルタイムで通勤時間も合わせて7時に家を出て19時に帰る毎日。 ずっと睡眠不足で疲れが取れない感じがある。 |
|---|---|
| 子どもとの時間が少ない | 子どもの睡眠時間を除くといっしょにいる時間が少ない。 ほとんど保育園に預けっぱなしで罪悪感がある。 |
| 夫婦間のバランスが悪い | どちらも働いているから負担の割合が気になる。 自分ばかり大変だと思って忙しさから相手を思いやれない。 |
| 家事がまわらない | 朝食や夕食を買ってきたもので済ませている。 洗濯や掃除も後回しでそんな自分がイヤになる。 |
| 自分を大切にできない | 自分のための休みがなくて自己肯定感が下がる。 リフレッシュできずストレスが溜まる。 |
どれも完璧にこなそうとした結果、体調を崩してしまうワーママもたくさん。「退職がちらつく理由」にはどのような内容があるのか、具体的な例を見ていきましょう。
とにかく体力的に限界
仕事と育児を両立するのは、想像以上に体力を消耗します。だって思い出してください、独身で働いていた頃を。あの頃でも仕事でクタクタ、足はパンパン。連勤を終えた次の日はお昼まで目が覚めない…。
それが今は、プラスで育児や家事。朝から晩まで仕事と家事・育児に追われる日々では、体力面も精神面においても、あっという間に疲れがピークに達してしまいますよね。
そしてワーママは「子どもがいることを理由にできない」と、仕事への責任感から自分で抱え込んだり、無理をしてしまったりしがちなため、中には限界が来るまで自分自身のSOSに気づかないケースも多いです。
休日においても、子どもたちが1日中家にいることが多いと面倒を見たり、家事優先の1日になってしまったりして、体力を回復する時間が取れない場合も…。



ワーママは平日も休日でも、体力を回復する暇がないのが問題なのよね…。休みがあったら子どもと公園に行きたいし、時間があったら美容院にも行きたいのに。疲れてやる気がでない。
子どもがすぐ体調を崩す
ワーママにとって、子どもの急な体調不良は大きな負担になります。保育園や小学校は集団生活ということもあり、あっという間に流行のウイルスを持って帰ってきます。
そして、病気のたびに仕事を休む必要があると「周りに迷惑をかけてしまう…。」という気持ちが生まれ、精神的な負担になることも。
お休みが続くと、職場に連絡することを考えるだけで動機が…。そんな状態が続くと、こんなに迷惑をかけるなら辞めてしまおうと考えてしまうもの。会社の上司から「あまり休まれては困る」と言われ、退職を選択するママもいます。
子どもはいつ病気にかかるかもわからないため、病気のたびに急な休みを取ることに悩むワーママが多いのが実情です。



頼れる親族も近くにいないしな…。
あれ?夫が交代で休みを取ってくれればいい話なのでは?
いや、これを言い出すと止まらない!
家事が後回しで家が荒れている
働いていると、家事が後回しになりがちです。夜帰宅したら、シンクに残った朝の食器を片付けるところからスタート。着る服を洗濯機から探し出す毎日。
それは、限られた時間とエネルギーの中で優先順位を付けた結果。
「仕事で疲れている…。」「でも子どものことはやらなくては…。」と優先順位を付けていくと、結果的に家事が後手に回ってしまうのです。
家事が滞ると家の中が散らかり、料理も手抜きになりかねないため、そんな自分に対して罪悪感を抱いてしまうワーママもいます。


子どもとの時間を優先したい
子どもが成長していく過程で「できるだけ一緒に過ごしたい」という気持ちは強くなるものです。子どもはあっという間に成長してしまうため「今は成長を近くで見守りたい」と考えるのは、ごく自然なこと。
とくに、保育園や学校に行くのを見送っていると「もう少し一緒に過ごせたら」という思いが強くなりますよね。そのため、退職して子どもとの時間を優先したいと考えるワーママが少なくないのです。
・保育園で子どものお迎えが1番最後だったとき
・試し行動などがあり愛情不足が不安になったとき
・子どもが知らない間に出来ることが増えていたとき
・近所の親子が楽しそうに公園で過ごしている姿を見たとき
・いつの間にか子どもが大きくなったと実感したとき
なぜ「退職はもったいない」と言われるのか
なにも考えなければ「子どもといっしょにいたい」「体力的に難しい」という理由があれば退職一択。しかし、それを思いとどまるのはやはり退職するのはもったいないという思いからではないでしょうか?
ではなぜ「退職はもったいない」のか…?ここからは、退職がもったいないと理由や、対処法などについて掘り下げていきます。退職をするかしないかを、もう一度考える力になれれば幸いです。
キャリアが絶たれる
「退職」は、今まで積み上げてきたキャリアが断たれることを意味しています。積み上げた経験は、やむを得ず転職を選んだときにも自分の武器になります。
キャリアを継続するためには、周囲の協力や職場の充実した制度も必要不可欠。難しい問題です。
- パターン①子どもが生まれたのち退職
-
・20歳/短期大学卒業後に就職
・27歳/結婚・妊娠・出産
・28歳/両立に限界を感じ退職
(勤務歴8年) - パターン②子どもの小学校入学を機に退職
-
・20歳/短期大学卒業後に就職
・27歳/結婚・妊娠・出産
・28歳/時短勤務を申請
・33歳/子ども小学校入学を機に退職
(勤務歴13年) - パターン③調整しながらなんとか継続
-
・20歳/短期大学卒業後に就職
・27歳/結婚・妊娠・出産
・28歳/時短勤務を申請
・33歳/子ども小学校入学を機にパートに
・39歳/子ども中学校入学を機にフルタイムに
(勤務歴20年以上~)
ワーママの場合、退職すると、仕事や時間に追われなくなりますが、一般的な独身の社会人と違い「子どもの風邪で急に休まれては困る」という会社が多いため、再就職が難しいのです。
時短やフレックス、勤務形態の切り替えが可能であれば、その時々の事情に合わせて臨機応変に調整するのが得策です。
しかし、退職を選んで今欲しい時間を手に入れる選択もよし。資格を取得したり、無理のない範囲でパートしてみたり、退職後の行動次第で、選択肢を広げることはできますよ。
大幅に収入が減る
ここをネックに感じているワーママが多いのでは…!退職してしまうと、家庭の収入が夫1人分になってしまうため、金銭面での不安が増します。
一馬力だけでは生活が厳しくなる可能性もあり、将来への貯蓄や子どもたちの教育資金の蓄えも難しくなるかもしれません。
家庭によって違いは大きいと思いますが、専業主婦家庭と共働き家庭の一例を比べてみましょう。
| 項目 | 専業主婦家庭 | 共働き家庭 |
|---|---|---|
| 夫の年収 | 500万円(会社員) | 500万円(同条件) |
| 妻の年収 | 0円(専業主婦) | 400万円(正社員・フルタイム) |
| 世帯年収(合計) | 500万円 | 900万円 |
| 所得税・住民税・社会保険料など | 約20% | 約25%(共働きで社会保険2人分) |
| 区分 | 専業主婦家庭 | 共働き家庭 |
|---|---|---|
| 年収 | 500万円 | 900万円 |
| 手取り(税・保険料差し引き後) | 約400万円 | 約680万円 |
| 差額(年間) | +280万円 |
つまり、共働き家庭のほうが年間で約280万円多く手取りがある計算になります。月換算で見ると約 23万円の差 です。もちろん共働き家庭には、ここから保育料・家事外注・通勤費 などの追加コストがかかります。
この収入を退職でなくしてしまうのは確かに「もったいない」と言われてしまうもの。現状が大丈夫だとしても、収入源1つで生活を保っていくのは簡単ではありませんよね。
社会とのつながりが減る
退職すると「育児中心の生活」になり社会とのつながりが減ってしまいます。
仕事をしていると、社会とのつながりや、同僚や取引先とのやり取りがあり、人間関係が築かれるので刺激を受けられますよね。
しかし、退職を選んでしまうと、人との関わりや社会的ネットワークが失われるため「寂しさ」や「孤独感」を生む場合があるんです。
とくにワーママにとって社会とのつながりは「自分が母親以外の役割を持っている」実感を与えてくれるため、失うのが「惜しい」と感じる場合も多いようですよ。
「子どもが小学校になれば落ち着くから」は本当?
周囲から「今が辛抱」「小学校になったら楽になるから」と言われることはありませんか?
子どもが成長してできることが増えることで、小学校に上がれば育児も楽になるという考えを持っている人も多いですが、必ずしもそうとは限りません。
・学童に入れるかどうかの問題
・保育園より学童の方が預かり時間が短い問題
・小学校4年生で学童終了問題
・勉強や習いごとの家庭でのサポート問題
・長期休暇や急な昼帰り問題
・学校行事やPTA活動の負担問題
・保育園同様、集団生活による感染症問題
むしろ…手がかからなくなる代わりに、預かり時間による物理的な問題が生じてしまいます。実は私も同じ理由で退職を決意しました。



保育園に7時まで子どもを見てもらっていたとして、学童に上がって6時半までとなるともう詰み。周囲に頼れる人がいる、または勤務時間を調整してもらえる環境がないと難しくなります。
夫や親族にも学校行事に出てもらえるように相談し、1人で全てを抱え込もうとしないでくださいね。というのは建前で、それができていれば退職は考えませんよね。げげげげ。


退職前に検討!「辞めなくてよかった」と後悔しないように
退職を決断する前には「働き方を変えることはできないか?」や「もし退職を選択した場合、金銭的な不安はないか?」などは考えておくべきです。
なぜなら、辞めた後に後悔するワーママもいるため。退職せずに今の仕事を続けられれば、キャリアが途切れることも会社の人とのかかわりが疎遠になってしまうのも防げますよね。
後悔しないためには、慎重に検討することが大切です。
働き方を変えることはできないか?
退職を選択する前に、働き方や家庭の柔軟性を考え、どうにかして今の仕事を続けられないか見直すことは重要です。
近年、リモートワークやフレックス制度を導入している企業も多いため、働き方を変えられないか1度確認してみましょう。
子どもがまだ小さい間は、時短勤務を申請できるところも多いですよ。夕方、1時間早く帰れるだけでも全然違います!また、働き慣れた場所であえてパートに降格するという選択肢も。
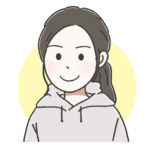
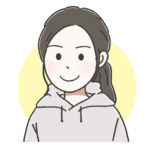
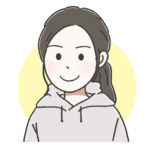
自分が知らなかった制度があるかも!
まずは「勤務継続が難しい」と相談してみては?
夫や親族との役割分担を再検討できないか?
家庭では、ママに負担が偏りすぎないよう、家事や育児の役割分担について話し合うことも大切です。退職は「個人の決断」ですが「家族の暮らしを再設計するきっかけ」にもなります。
誰がどの家事をどの程度担うか、現実的に話し合ってみましょう。現状を紙に書いてどれだけ負担が偏っているか可視化するのもgood。
話し合いを通じてお互いの希望や不安をすり合わせられれば、安心して新しい生活を始める準備ができるはずです。



無理って言うなら便利家電や家事代行を検討!
当たり前の権利でしょ?


退職後も金銭面で不安なくやっていけるか?
退職の後、金銭面的に「不安なく生活が送れるか」を考える必要があります。
金銭面の見通しを立てておくと、退職するかどうかの判断基準になり「退職する」と決めた後も気持ちを安定させてくれます。
貯金や生活費、将来の支出もしっかりシミュレーションして、退職後の生活がどのようになるかを考えておきましょう。
フルタイムにこだわらず、数時間パートとして無理なく働く選択などもありますよ。
まとめ
ワーママとして退職を考える理由はさまざまですが、本当に最適な選択かどうかを再考するのは大切です。
自分のキャリアや家庭のバランスを見直し、様々な視点から「どんな選択がいいのか」後悔しないように考えてみてくださいね。
それでも「やっぱり辞めたい」と思ったときは、「辞める勇気」を持って、自分のために行動してみましょう。この記事が、退職に悩むワーママさんの力になれたら幸いです。